相続に必要な法的手続きは?遺品整理の義務や死後に行う手続きも解説
故人の遺品整理と相続手続きは、深い悲しみの中で取り組まなければならない重要な責務です。法定相続人には、遺品の適切な管理や処分、相続に関するさまざまな法的手続きが求められます。
また、相続手続きには期限があり、手順を誤ると後々の手続きに支障をきたす可能性もあります。
本記事では、遺品整理の義務と責任、死後に必要な法的手続き、相続手続きを円滑に進めるためのポイントについて解説していきます。
また当社エコトミーでは、一都三県を対象に不用品回収や遺品整理サービスを提供しています。
不用品回収や遺品整理に関する些細なご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を読むための時間:5分
遺品整理の義務
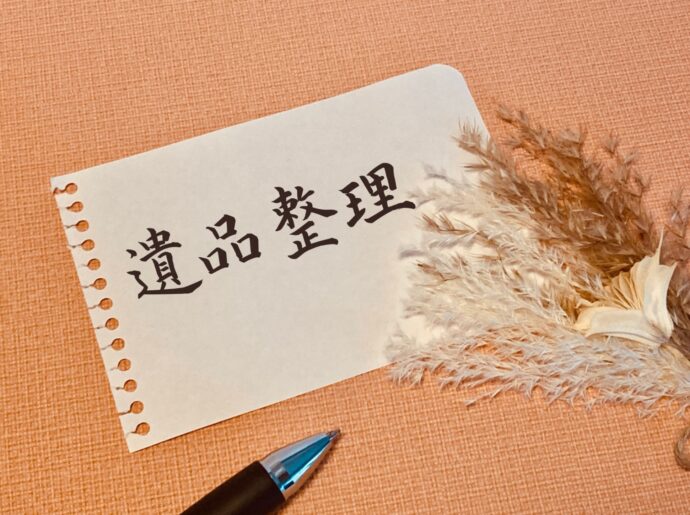
故人の遺品整理は、誰がどのように行うべきか、その義務と責任について解説します。
遺品整理の目的
遺品整理の主な目的は、以下のとおりです。
- 遺品の適切な保管と管理
- 相続財産としての価値評価
- 相続人間での公平な分配
- 不要品の適切な処分
とくに重要なのが、遺品の保管と管理です。故人の財産は相続が確定するまで、適切に保管する必要があります。
遺品整理を行う人
遺品整理は、主に法定相続人が行う必要があります。相続の順位に従って、以下の方々が責任者となります。
- 配偶者(最優先の相続人)
- 子供(第一順位の法定相続人)
- 両親・祖父母(第二順位の法定相続人)
- 兄弟姉妹(第三順位の法定相続人)
相続放棄と遺品整理
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄する法的手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となるため、総合的な判断が必要となります。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。
しかし、相続放棄をしても遺品に関する全ての責任が消えるわけではありません。民法では遺品の処分を行うと法定単純承認とみなされるため、原則として遺品整理はできなくなります。一方で、遺品の管理義務は残り、以下のような場合には遺品整理が必要となることがあります。
- 財産管理人が未選任の場合の財産管理義務
- 故人が孤独死した場合の特殊清掃
- 賃貸物件の連帯保証人としての責任
遺品整理を行う場合は、日持ちしない食品など資産価値のないものは処分可能ですが、価値のある物品の処分は避ける必要があります。誤って財産的価値のあるものを処分してしまうリスクを避けるため、専門の遺品整理業者に依頼することをおすすめします。
このように、相続放棄は慎重な判断と適切な対応が求められる重要な法的手続きです。相続放棄を検討する際は、遺品整理との関係性を十分に理解し、必要に応じて弁護士や専門家に相談しましょう。
故人の死後に行うべき手続き
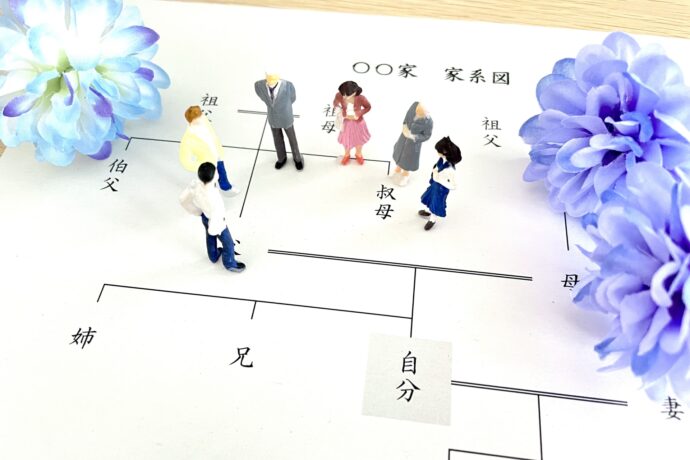
大切な方を亡くされた後、悲しみの中でもさまざまな手続きが必要となります。これらの手続きは、法律で定められた期限内に行う必要があり、手順を誤ると後々の手続きに支障をきたす可能性もあります。
ここでは、故人の死後に必要な手続きの内容と期限、必要書類について、優先順位順に解説します。
死亡届の提出
死亡届は、全ての手続きの基点となる重要な届出です。医師による死亡診断書を添付して、7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。この手続きにより死亡が法的に証明され、以降の手続きが可能となります。提出すると火葬許可証が発行されるため、葬儀を執り行う前に必ず行う必要があります。
年金の受給停止手続き
故人が年金を受給していた場合、14日以内に年金事務所への届出が必要です。手続きが遅れると過払い分の返還を求められる可能性があるため、できるだけ早めに対応しましょう。遺族年金の受給資格がある場合は、この時点で相談することをおすすめします。
健康保険資格喪失手続き
健康保険も14日以内に喪失手続きを行う必要があります。故人が会社員だった場合は会社が代行することもありますが、国民健康保険の場合は遺族が市区町村役場で手続きを行います。保険証の返却を忘れずに行いましょう。
公共料金などの引き落とし口座の変更
電気、ガス、水道などの公共料金の契約が故人名義になっている場合は、名義変更が必要です。また、自動引き落としの口座も変更する必要があります。支払いが滞らないよう、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。
戸籍謄本の取得
戸籍謄本は、これらの手続きや今後の相続手続きで必要となります。複数必要になることが多いため、まとめて取得しておくと便利です。2024年3月以降は、本籍地以外の市区町村役場でも取得可能となっています。
相続に必要な法的手続き

相続に関する手続きは法律で定められた期限内に行う必要があり、手順を誤ると後々の手続きに支障をきたす可能性があります。また、財産の調査から相続税の申告まで、専門的な知識が必要な部分も多くあります。
遺言書の有無の確認
まず最初に行うべきは、遺言書の有無の確認です。遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになります。
自宅や貸金庫の確認のほか、公証役場で公正証書遺言の有無を確認することも重要です。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
相続財産(遺産)の調査
次に、相続財産の全容を把握します。プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い金など)も含めて、正確に調査する必要があります。この調査結果は、後の遺産分割協議や相続税申告の基礎となる重要な資料となります。
相続人の調査
戸籍謄本等を収集し、法定相続人を確定させます。相続人が一人でも漏れていると、後の手続きが無効になる可能性があるため、慎重な調査が必要です。また、代襲相続の可能性もあるため、必要に応じて故人の両親や兄弟姉妹の戸籍も確認します。
相続の承認・放棄の決定
相続人には、単純承認、限定承認、相続放棄の三つの選択肢があります。限定承認と相続放棄には期限(3か月以内)があり、家庭裁判所への申述が必要です。慎重に検討し、決定する必要があります。
遺産分割協議の実施
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法を協議します。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。協議が難航する場合は、家庭裁判所での調停も検討します。
相続税の申告・納付
最後に、相続税の対象となる場合は、期限内(10か月以内)に申告・納付を行います。正確な財産評価と適切な申告が重要で、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。
相続手続きを進めるために遺品整理で注意すること

相続手続きを円滑に進めるためには、遺品整理の段階から慎重な対応が必要です。とくに重要なのが、法的手続きに必要な書類の保管と、相続人間のコミュニケーションです。以下、具体的な注意点について説明します。
相続人全員の合意を得る
遺品整理を始める前に、必ず他の相続人に連絡を取り、合意を得ることが重要です。故人の遺品は相続財産の一部であり、独断での処分は後々のトラブルの原因となります。また、誰が中心となって整理を進めるのか、費用はどのように分担するのかなども、事前に決めておく必要があります。
重要書類の保管を徹底する
相続手続きには多くの書類が必要となります。とくに以下の書類は、誤って処分しないよう注意が必要です。
- 遺言書(見つかった場合)
- 預金通帳・印鑑
- 年金手帳・保険証
- 不動産関係書類
- 借金や負債の証明書類
これらの書類は、一時的に別の場所に保管するなど、紛失や破損を防ぐ工夫が必要です。
相続放棄への影響に注意
遺品の整理を始めることで、「相続の承認」と見なされる可能性があります。とくに借金など負債が心配される場合は、遺品整理を始める前に、相続放棄の要否を検討することが重要です。相続放棄は期限(3か月以内)があるため、早めの判断が必要です。
このように、遺品整理は単なる片付けではなく、相続手続き全体に影響を与える重要な作業です。不安な点がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
まとめ

遺品整理は法定相続人の重要な責務であり、相続手続き全体に影響を与える作業です。相続放棄をした場合でも、一定の管理義務は残ることに注意が必要です。
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、年金や保険の手続き、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告まで、多岐にわたります。それぞれの手続きには期限があり、計画的な対応が求められます。
遺品整理を進める際は、相続人全員の合意を得ること、重要書類の保管を徹底すること、相続放棄への影響に注意することが重要です。不安な点がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に早めに相談しましょう。
また、エコトミーでは、一都三県を対象に遺品整理や不用品回収サービスを提供しています。
遺品整理士の資格を持つスタッフが、お客様のご要望を丁寧にお聞きします。大切な遺品を雑に扱われる心配もありません。
「今日中に済ませたい」「不法投棄が心配」といった不安も解消。土日対応もご相談ください。見積もりは無料で、金額に自信があります。
最短即日で対応していますので、遺品整理や不用品回収の依頼を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

