遺品整理で遺言書が見つかった場合はどうする?手続きや注意点も解説
遺品整理の過程で遺言書を発見することは、決して珍しいことではありません。
しかし、その取り扱いには細心の注意が必要です。とくに自筆証書遺言や秘密証書遺言は、開封すると法的な問題を引き起こす可能性があります。
また、すでに遺産分割が完了している場合は、遺言書の内容によって再分割が必要になることもあり、相続人間の新たなトラブルの原因となることも。
この記事では、遺言書の種類ごとの必要な手続きから、家庭裁判所での検認の流れ、遺産分割後に発見された場合の対応まで、具体的に解説します。
突然の発見に慌てることなく、適切な対応ができるよう、重要なポイントをまとめました。
また当社エコトミーでは、一都三県を対象に遺品整理や不用品回収サービスを提供しています。
遺品整理や不用品回収に関する些細なご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を読むための時間:5分
遺品整理で遺言書が見つかった場合の対応
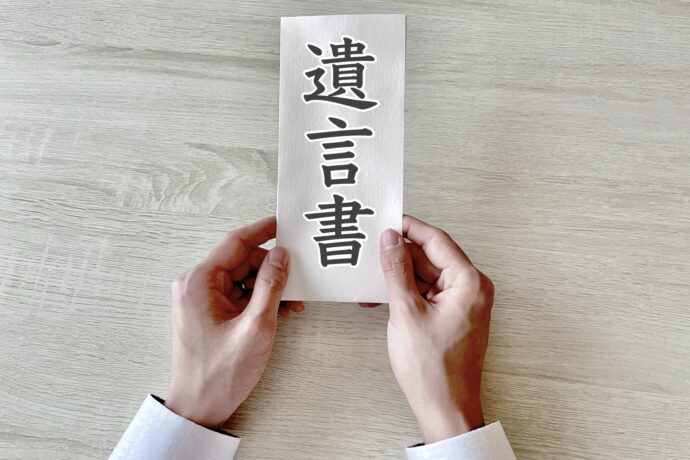
遺品整理で遺言書を発見することもあるでしょう。遺言書が見つかった場合、どのように対応すべきか事前に知っておく必要があります。
なぜなら、遺言書は種類によって必要な手続きが異なります。不適切な取り扱いは法的な問題を引き起こす可能性があるため、正しい知識と対応が必要です。
ここでは、遺言書の種類ごとに必要な手続きと注意点を解説します。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、信頼性の高い遺言の形式です。公証人の立会いのもとで作成され、原本は公証役場で保管されているため、その存在と内容の信頼性は極めて高いものとなります。
この形式の遺言書が見つかった場合、特別な手続きは必要ありません。直ちに内容に従って遺産分割を進めることができ、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、故人が自ら手書きで作成した遺言書です。この形式の遺言書を発見した場合、決して自分で開封してはいけません。
必ず開封されていない状態で家庭裁判所に提出し、検認を申請する必要があります。むやみに開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
検認手続きでは相続人全員が立会いのもと、遺言書の内容や形式が適法かどうかを確認し、その後で相続手続きに進むことになります。
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言は、遺言者が作成した内容を秘密にしたうえで、公証人が存在を証明する形式です。秘密証書遺言も、勝手に開封してはいけません。
この形式も自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が必要となります。公証人による証明の確認を経て、内容の開示へと進みます。
遺言書の検認手続きの流れ

不用品整理や遺品整理中に遺言書を発見した場合、法的な手続きに従って適切に対応することが重要です。
慌てて開封してしまうと法的な問題が生じる可能性があるため、正しい手順を知っておきましょう。
発見直後の対応
遺言書を発見したら、まず開封せずにそのまま保管することが最優先です。
とくに自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、開封は法律で禁止されており、違反すると5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
遺言書は安全な場所に保管し、他の相続人にも発見の事実を伝えましょう。
家庭裁判所での検認で必要な書類
遺言書の検認で必要な書類は、相続人の立場によってわかります。ここでは、共通する必要書類を紹介します。
- 遺言者の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 家事審判申立書
- 当事者目録
また、検認には収入印紙と郵便切手の費用が掛かります。
申立て書類の提出
準備した書類は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
検認期日は、他の相続人にも通知されますが、出席は申立人のみが必須となります。
検認手続きの実施
検認期日には、家庭裁判所で正式に遺言書が開封されます。裁判官と出席した相続人の立会いのもと、遺言書の形式や内容が確認されます。日付や署名などの重要な要素も詳しくチェックされます。
検認後の対応
検認が完了すると「検認済証明書」が発行されます。この証明書は、その後の相続手続きで重要な書類となります。
検認を経て正式に内容が確認された遺言書にもとづいて、具体的な相続手続きを進めていくことになります。
検認にかかる時間
遺言書の検認を家庭裁判所に申し立ててから、検認期日までには1ヶ月~2ヶ月かかります。そのため、遺言書を発見してから検認完了まではおおよそ2ヶ月~3ヵ月程度かかる場合もあります。
遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応

遺産分割を終えたあとに遺言書が発見された場合、その取り扱いには慎重な判断が必要です。
故人の意思を尊重しつつ、すでに行われた分割との調整が必要となるためです。ここでは、このような状況での適切な対応方法を解説します。
遺言書の法的効力
遺言書は、被相続人の死亡時から自動的に効力を持ちます。
そのため、遺産分割が完了した後に発見された場合でも、原則としてその内容が優先されます。これは、故人の最後の意思を尊重するためです。
相続人間の合意による解決
発見された遺言書の内容について、相続人全員が合意すれば、すでに行われた遺産分割の内容を維持することも可能です。
遺産分割のやり直しが必要な場合
特定の状況下では、遺産分割の見直しが必要になることがあります。
- 遺言執行者が指定されている場合
- 遺言書に遺産分割禁止と記載されている場合
- 遺言書が隠されていた場合
このような場合は、遺言書の内容にもとづいた新たな分割協議が必要となります。
トラブル防止と解決策
遺言書の発見は、相続人間の新たなトラブルの原因となることがあります。とくに問題となりやすいのは、以下のような場合です。
- 既存の分割と大きく異なる内容の場合
- 財産がすでに処分されている場合
- 分割された財産が使用されている場合
このような状況では、専門家への相談を通じて適切な解決策を見出すことが重要です。
時間経過による制約
発見までに時間が経過している場合、遺言書の内容通りの再分割が困難なケースもあります。
- 相続財産がすでに処分されている
- 金銭が使用されている
- 不動産の名義変更が完了している
このような場合は、金銭による調整など、代替的な解決方法を検討する必要があります。
専門家への相談
このような複雑な状況では、専門家のアドバイスが不可欠です。以下のような専門家に相談することをおすすめします。
- 弁護士:法的な対応方法の相談
- 税理士:税務上の影響の確認
- 司法書士:手続き面でのアドバイス
専門家のサポートを受けることで、より適切な解決策を見出すことができます。
スムーズな解決のためには、相続人全員が冷静に話し合い、必要に応じて専門家の助言を受けながら、適切な対応を進めることが重要です。
遺品整理中の遺言書発見における注意点
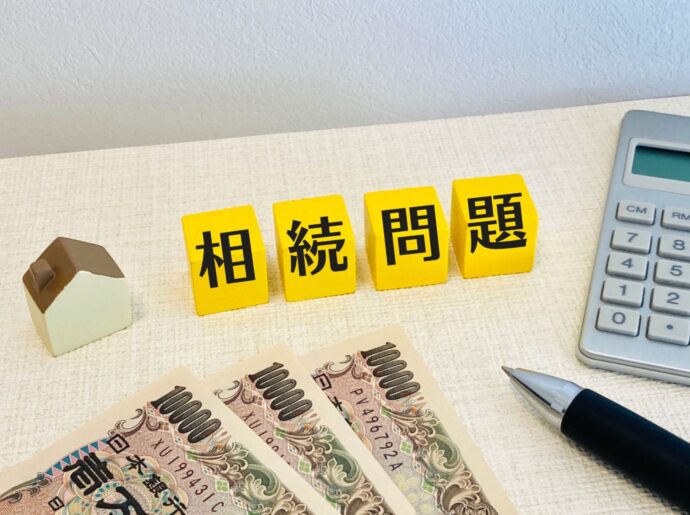
遺言書を発見した場合に最も注意すべき点は、決して開封しないことです。
とくに自筆証書遺言や秘密証書遺言は、開封すると5万円以下の過料の対象となります。発見したら、安全な場所に保管し、家庭裁判所での検認手続きを進めましょう。
また、すでに遺産分割が完了している場合は、遺言書の内容によって再分割が必要になることもあります。
複数の遺言書が見つかった場合は、原則として新しい日付のものが有効となります。
いずれの場合も、冷静な対応と適切な手続きの遵守が重要で、不明点がある場合は必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
独断的な行動は避け、他の相続人との情報共有も忘れずに行いましょう。
まとめ

遺言書の取り扱いは、その種類によって大きく異なります。
公正証書遺言の場合は特別な手続きは不要ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、必ず家庭裁判所での検認が必要です。
検認手続きには1〜2ヶ月程度かかり、遺言者の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など、複数の書類が必要となります。
すでに遺産分割が完了している場合でも、発見された遺言書は原則として法的効力を持ちます。ただし、相続人全員の合意があれば、既存の分割を維持することも可能です。
複数の遺言書が見つかった場合は、原則として新しい日付のものが有効となります。
不明点がある場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
また、エコトミーでは、一都三県を対象に遺品整理や不用品回収サービスを提供しています。
遺品整理士の資格を持つスタッフが、お客様のご要望を丁寧にお聞きします。大切な遺品を雑に扱われる心配もありません。
「今日中に済ませたい」「不法投棄が心配」といった不安も解消。土日対応もご相談ください。見積もりは無料で、金額に自信があります。
最短即日で対応していますので、遺品整理や不用品回収の依頼を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

