遺言書とエンディングノートの違いとは?併用すべき?保管場所はどこ?
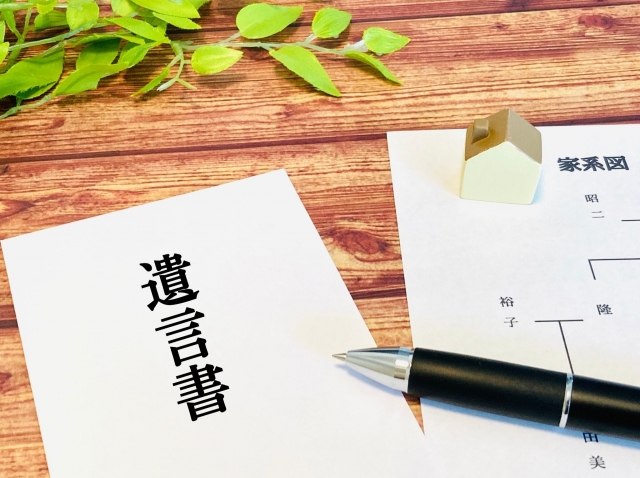
終活の一環として、残される家族のために遺言書とエンディングノートを作成する方は少なくありません。
これらは似た意味で使われることがありますが、明確に役割に違いがあることをご存知でしょうか?
本記事ではエンディングノートと遺言書の概要や違い、疑問にお答えしていきます。
終活でエンディングノートや遺言書の作成を考えている方は、本記事を参考にして使い分けられるようになりましょう。
この記事を読むための時間:5分
遺言書とは?
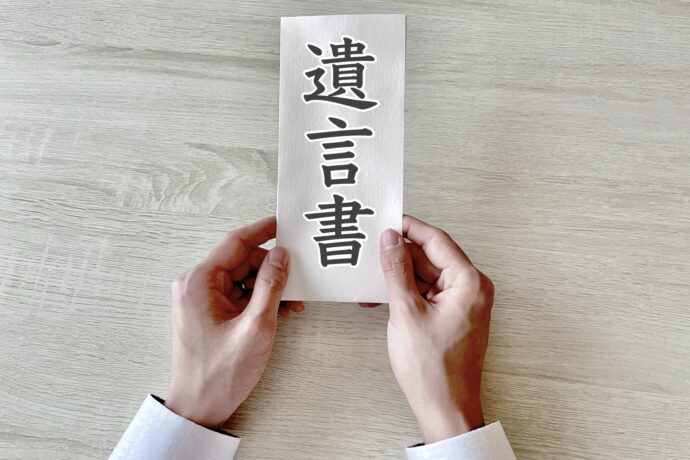
遺言書は、誰に何を相続するのか、意思をはっきり伝えるために活用されます。
遺言は死亡してから効力を発揮するものですが、決まった形式で作成しなければ無効となってしまいます。
主に以下の3つの形式で遺言書は作成されます。
-
自筆証書遺言
-
秘密証書遺言
-
公正証書遺言
それぞれ解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自身で作成し、紙とペンを用いて自筆します。
「相続させる」もしくは「贈与する」とはっきり記載しなければならず、書き方に不備があると無効になります。
また、作成した年月日も正確に記載し、署名と押印が必要になります。
検認の手続きが必要ですが、法務局に保管してもらう場合は開封時の検認が必要なくなります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にした状態で、遺言書の存在だけを証明してもらえる特徴があります。
作成した遺言を公証役場に持って行くため、内容を知られてしまう心配がありません。
公証役場に問い合わせることで、遺言の有無を確認できるため、遺言があると分かれば自宅を探しましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人が文章にし、作成してもらう遺言書です。
自筆できない方でも作成でき、病院に公証人を呼べば入院中の方も作成できます。
公証人が作成するため、不備があり無効になることがありません。検認手続きの必要もありません。
エンディングノートとは?

エンディングノートは残される家族のために、自分の情報や伝えたい思い、相続について、資産状況、遺言の保管場所などを記載するものです。
残される家族のためでもありますが、自分の情報を書き出すことで自分自身と向き合ったり、今後について考えるきっかけにもなります。
決められた書き方がなく、自由に記載できるのがエンディングノートの特徴です。
エンディングノートと遺言書の違いとは?

エンディングノートと遺言書は同じような役割を持つ部分もありますが、いくつかの違いがあります。
-
目的の違い
-
法的効力の違い
-
書き方の違い
-
開封方法の違い
上記の4つについて解説します。
目的の違い
遺言書は相続の手続きを正当に進めるためだけに用いられます。
一方、エンディングノートにはさまざま目的があります。自分のことや伝えたいメッセージ、葬儀のこと、遺言書の場所などを記載することが可能です。
エンディングノートにも相続について記載できますが、自分の希望を記載するだけで、遺言にはなりません。
法的効力の違い
法的効力にも違いがあります。
まず、エンディングノートには法的効力がありません。
エンディングノートにどれだけ相続について記載しても、その通りの相続される可能性は低いです。希望にしかならないため注意しなければなりません。
一方、遺言書には法的な効力があるため、遺言書を作成すれば法定相続人より優先して相続されます。
書き方の違い
エンディングノートには書き方の決まりがありません。そのため書く内容も自由ですし、好きなタイミングで追記できます。
しかし、遺言書には明確な書き方があります。正しい書き方でなければ効力が発揮されず無効になってしまいます。
また、遺言書には複数の種類があり、種類によって書き方が変わります。年月日や押印など、細かい要件を満たす必要があるため、注意して作成しましょう。
開封方法の違い
エンディングノートには開封という概念がなく、生前でも確認できます。
エンディングノートという名称ですが、生前にも活用するタイミングがあるため、いつでも開封でき、書き直すこともできるのが当たり前です。
一方、遺言書は勝手に開封してはいけません。公正証書遺言のように検認の必要がない遺言もありますが、家庭裁判所での検認手続きをしてから開封することになります。
エンディングノートと遺言書に関するよくある質問

エンディングノートと遺言書に関するよくある質問をまとめましたのでご確認ください。
-
エンディングノートと遺言書は併用すべき?
-
ノートに書かれた遺言でも遺言書になることはある?
-
遺言書はどこで保管すべき?
-
遺言書の作成にはいくらくらいかかる?
-
遺言に有効期限はある?
それぞれ解説します。
エンディングノートと遺言書は併用すべき?
エンディングノートと遺言書は併用すべきです。
希望通りの相続を進めるために遺言書が必要になります。エンディングノートに相続の希望を記載するだけでは相続できません。
また、遺言書は決まった形式で記載する必要があるため、遺族にメッセージを残すことはできません。気持ちを伝えるためにはエンディングノートを活用すべきです。
ノートに書かれた遺言でも遺言書になることはある?
法的な要件を満たしていれば遺言になります。
自筆証書遺言の場合、書く用紙の指定はないため、ノートやメモ帳に書いても問題ありません。
遺言書はどこで保管すべき?
遺言書は種類によって保管方法が変わります。
自筆証書遺言の場合、自宅で保管するか、法務局で保管してもらうかのどちらかになります。
秘密証書遺言の場合は自分で保管しなければなりません。
公正証書遺言の場合は、公証役場で保管してもらいます。
自宅で保管する場合、机の引き出しやタンスの中、貴重品を保管している場所、鍵付きの収納場所、仏壇周り、金庫などを利用するとよいでしょう。
遺言書の作成にはいくらくらいかかる?
自筆証書遺言の作成にはお金がかかりません。しかし、遺言書保管制度を利用して法務局に遺言書を保管してもらう場合は3,900円の費用がかかります。
公正証書遺言の場合、相続する金額によって変動しますが、5万円以内に収まることが多いです。しかし、公証人に出張してもらう場合は5万円以上になることもあるでしょう。
秘密証書遺言の場合は、手数料として11,000円の費用がかかります。
遺言に有効期限はある?
遺言に有効期限はありません。
遺言は一度作成すれば、死後に効力を発揮し続けます。
しかし、有効期限がなくても作成し直さなければならない場合があります。
たとえば、遺言に不動産を相続される旨を記載していたものの、不動産を売却してしまった場合、遺言の内容を書き換える必要があります。
それ以外にも配偶者に相続予定だったものの、離婚が原因で相続を止める場合なども同様です。
有効期限がなく、ずっと効力を発揮するものだからこそ、書き換える必要があることを覚えておきましょう。
まとめ:エンディングノートと遺言書は両方作成しよう

エンディングノートや遺言書の作成は終活において重要な作業となります。
生前整理をしなければ、残された家族に負担を強いることになります。しかし、エンディングノートや遺言書を作成できるのは自分だけです。
相続先を決定することも、家族への想いを残すこともあなたにしかできません。これらは終活の作業で優先して行うことをおすすめします。
エコトミーでは終活をサポートさせていただきます。
遺品整理や生前整理、終活などの質問も受け付けておりますので、気になることがあればご連絡いただければと思います。
